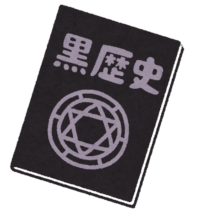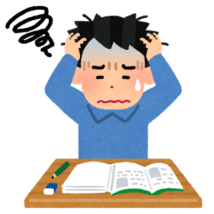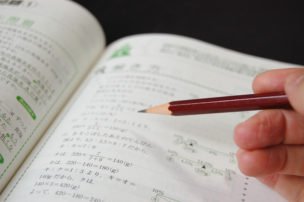塾長です。
今日は非科学的なことを書きます(笑)
勉強は「できない」がスタート地点
私はいつも
「できない」を「できる」に変えるのが「勉強」だ!
と言っているのですが、
まぁ、
この考えを変えるつもりは今のところないです。
すると、
「勉強」は必ず「できない」からスタート!
することになるわけです。
もちろん「できない」を発見するために、
事前準備の「作業」として、問題を解くなどする必要があります。
ここで問題集を解くのが勉強だと勘違いしないことが大切ですが、
これは勉強の「効率」の話ですので、今回は書きません。
今回は「できない」からスタートしたら、
次に何を行動するか?
について考えたいと思います。
粘るときと諦めるとき
「できない」に直面したとき、必ずしも「できる」ようになるとは限りませんよね。
そのとき「できない」をどうやって判断しますか?
とりあえず、少なくとも2つの選択肢があるわけです。
- 粘るか?
- 諦めるか?
しかし2つに見えて、実は1つなんですよね。
- 諦めるまで何時間チャレンジするか?
だって人間はデジタルではなくてアナログですもん。
いきなりスパッと0か1かで判断できません。
つまり「難しい」とは、この時間の長さで表現できることが多いと思います。
そして、この時間の長さの感覚は、人によって違ってくると思うんですよね。
努力を推し量る
例えば、これまでの人生を振り返って、
「できない」を「できる」に変える勉強の中で、
最も難しかったときを振り返ってみましょう。
そのとき、乗り越えるまでに要した時間は、どれくらいだったのでしょうか?
- 10分?
- 1時間?
- 1日?
- 1週間?
- 1か月?
- 3か月?
- 半年?
- 1年?
もちろん、厳密に計ることはできないのでしょう。
あくまでも感覚ですよ、感覚。
感覚的には、
この時間が長い人の方が、高いスキルを身に着けている
と僕は感じています。
このような話は、個人の価値観にとても大きく左右されます。
賛成、反対、大反対・・・
長くチャレンジすりゃ良いってもんじゃない・・・
いろいろあります。
でも、私の価値観は、そういう感覚なんですよ。
逆に、そういう感覚だからこそ、自分に適性があるかないかも、ちゃんと考えるべきだと思うんですよね。
適性とは「努力できる分野」のこと?
適性があるってことは、
- 1年ずっと努力できる
- 10年ずっと努力できる
ということで、
適性がない、ということは、
- 10分で諦める(諦めた方が良い)
- 1時間で諦める(諦めた方が良い)
という風に考えられるんですよ。
で、繰り返しになりますが、ここで価値観が出てくるんですよ。
「諦める」を一律に悪いことだとみなす価値観と、戦略的撤退だとみなす価値観。
私は戦略的撤退を選びますね。
その代わり、これと決めたら、けっこう時間を取ります。
1年とか3年とか、10年とか続くのは、さすがに結果論ですかね?
そこまで言わないまでも、選んだら、それなりに時間と体力を突っ込みます。
選ばないとね、得意なものに集中できないし、得意にもならないんですよ。
とある開発のお仕事から
昨年の冬に、とある開発案件(プログラミングの仕事)をやらせてもらったんですよ。
3か月間くらいのプロジェクトでした。
(塾長のお仕事は塾だけではないです)
その中の、とある機能の実現が、けっこう難しくて。
考えたり調べたりするのに2か月かかりました。
ちなみに、その考えをプログラミングで実現するのは1日でした。
プログラミングって、まぁ、だいたいそういう世界です。
プログラムを書くよりも、考える方が10倍くらい時間がかかります。
(学生の皆さん、ご安心ください。高校や大学で習ったこと、仕事でめっちゃ使いますよ!)
ほんと、ヤベーな・・・とか思って、
生徒たちが帰った後、
1人ポツンと教室に残って、
うーん、うーん、と考える。
2、3回くらい徹夜して考えました。
その間に色々なノウハウが身につきました。
それじゃぁ、それが辛くて嫌だったのかと言えば、別に嫌じゃない。
むしろ、正しく動いた時には嬉しかったのです。
だから私は、そういう方向に適性があるのかもしれません。
いや、あると思いたい(笑)
時間の感じ方を自覚してチャレンジする
適性があるとか、難しくても諦めないとか、
逆に
適性がないとか、難しくて諦めるたり撤退したりするとか、
っていうのは、
同じ時間をどう感じるか、
ってことから行動が変わる結果なのでしょう、きっと。
科学的な根拠はないですよ。感覚ですよ、感覚。
学校の勉強で、オール5を取れる人は取ればよいし、取るだけの努力をすればよいと思いますが、
逆にオール5の可能性に見切りをつけて、戦略的な撤退をするのもありだと思いますよ。
どっちの方が偉いとか偉くないとか、そういう単純な判断は無いと思うんですよね。
できる方でやれば良いと思います。
選んで集中し、その代わり大きな時間を費やして頑張ってみる。
他人から見たら、変態的な努力をしてみる。
もしも、それが嫌じゃないとしたら、きっと適性があるのだと思います。
まぁ、やってみないと分からないのですがね。
ちなみに学生の皆さんは、子供の特権があります。
大人に比べたら、子供の方が圧倒的に守られているという特権です。
つまり、
社会に守られているうちに、
失敗を恐れず、
色々とやってみたらよいでしょう。
進学実績
卒塾生(進路が確定するまで在籍していた生徒)が入学した学校の一覧です。
ちなみに合格実績だけであれば更に多岐・多数にわたります。生徒が入学しなかった学校名は公開しておりません。
国公立大学
名古屋大学、千葉大学、滋賀大学、愛知県立大学、鹿児島大学
私立大学
中央大学、南山大学、名城大学、中京大学、中部大学、愛知淑徳大学、椙山女学園大学、愛知大学、愛知学院大学、愛知東邦大学、愛知工業大学、同朋大学、帝京大学、藤田保健衛生大学、日本福祉大学
公立高校
菊里高校、名東高校、昭和高校、松陰高校、天白高校、愛知教育大学附属高校、名古屋西高校、熱田高校、緑高校、日進西高校、豊明高校、東郷高校、山田高校、鳴海高校、三好高校、惟信高校、日進高校、守山高校、愛知総合工科高校、愛知商業高校、名古屋商業高校、若宮商業高校、名古屋市工芸高校、桜台高校、名南工業高校、菰野高校(三重)
私立高校
愛知高校、中京大中京高校、愛工大名電高校、星城高校、東邦高校、桜花学園高校、東海学園高校、名経高蔵高校、栄徳高校、名古屋女子高校、中部第一高校、名古屋大谷高校、至学館高校、聖カピタニオ高校、享栄高校、菊華高校、黎明高校、愛知みずほ高校、豊田大谷高校、杜若高校、大同高校、愛産大工業高校、愛知工業高校、名古屋工業高校、黎明高校、岡崎城西高校、大垣日大高校
(番外編)学年1位または成績優秀者を輩出した高校
天白高校、日進西高校、愛工大名電高校、名古屋大谷高校
※ 成績優秀者・・・成績が学年トップクラスで、なおかつ卒業生代表などに選ばれた生徒
名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!
★ 直接のお問い合わせ ★
――――――――――――――――――――――
個別指導ヒーローズ 植田一本松校
〒468-0009
名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F
TEL:052-893-9759
教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL